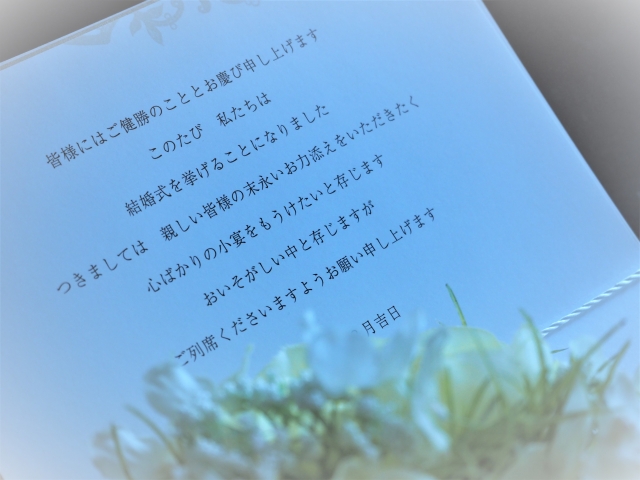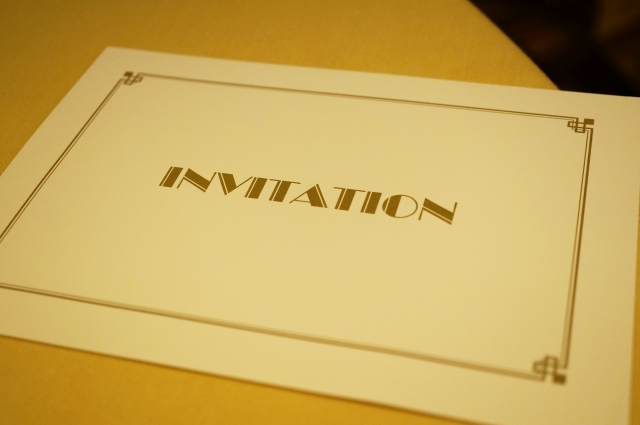こんにちは!
ウエディングプランナーとして、10年以上に渡り約1000組の結婚式をお手伝いしてきた茂木です♪
今日も新郎新婦様に一番近い存在として皆様の参考になる記事をお届けいたします。
今回は「テーブルレイアウトのルール」についてご紹介します。
テーブルレイアウトとは?
そもそもテーブルレイアウトとは、ゲストに座ってもらうテーブルの配置や席次のこと。
せっかくなら、ゲストが心地よく過ごせるテーブルレイアウトにしたいですよね^^
そこで今回は、テーブルレイアウトの種類や、テーブルレイアウトを決めるときに気をつけたいことについてご紹介していきます。
テーブルレイアウトの種類
披露宴会場のテーブルレイアウトとして、以下の3つが代表的なレイアウトです。
【1】円卓テーブルを使った「ちらし型」 【2】長テーブルを使った「くし型」 【3】メインテーブルを設けない「オーバル型」
まずは、それぞれの特徴とメリット•デメリットについてご紹介したいと思います^^
【1】円卓テーブルを使った「ちらし型」
新郎新婦のメインテーブルの前に、円卓をバランスよく配置する「ちらし型」。
披露宴では定番になっているスタイルなので、一番イメージがしやすいスタイルでもあると思います。
▪️「ちらし型」のメリット
「ちらし型」の一番のメリットは、同じテーブルに座るゲストの顔が見渡せるため会話が弾みやすく、和やかな雰囲気になることです。
ゲストの人数が増減したときにも、ひとつのテーブルに座る人数やテーブルの数を調整することで対応できるので安心^^
また、ゲストが動きやすいというメリットもあるので、ゲストとたくさん写真を撮ったり、気軽に触れ合えるウェディングにしたいカップルにはオススメです♪
▪️「ちらし型」のデメリット
「ちらし型」は、他のテーブルレイアウトに比べると、一番会場スペースの大きさが必要になります。
また、新郎新婦に背を向けて座るゲストが出てくるため、新郎新婦やムービーなどの演出が見にくい席があるという点もデメリットのひとつです。
【2】長テーブルを使った「くし型」
「くし型」のテーブルレイアウトは、新郎新婦のメインテーブルに向かって、長いテーブルを垂直に配置するレイアウトのことを言います。
皇室の晩餐会などでも取り入れられている、最も正式なスタイルでもあります。
▪️「くし型」のメリット
くし型の配置は多数のゲストが座れるのが大きなメリットのひとつです。
そのため、ゲストの人数が多いカップルにぴったりのレイアウトです。
また、「くし型」は皇室の晩餐会などでも取り入れられているスタイルなので、格式の高い結婚式をイメージしているカップルにもオススメです♪
▪️「くし型」のデメリット
長い大きなテーブルを使う「くし型」のレイアウトだと、隣や向かいなど近くに座っている人としか会話できないので、ゲスト同士が交流しにくいというデメリットが。
また、他のレイアウトに比べてパーソナルエリアが狭くなるので、ゲストが若干窮屈に感じてしまうことも。
イスとイスの間を広めに配置するなど、スペースにゆとりを持たせるとゲストも動きやすく、過ごしやすくなるのでオススメです^^
【3】メインテーブルを設けない「オーバル型」
「オーバル型」は、新郎新婦のメインテーブルを設けずに、新郎新婦もゲストと一緒に同じ楕円状のテーブルに座るスタイルのことを言います。
10~15名くらいの少人数のウェディングパーティーによく見られるレイアウトです。
▪️「オーバル型」のメリット
「オーバル型」のレイアウトの最大のメリットは、新郎新婦も一緒に座ることができるので、ゲストとの会話を楽しむことができることです。
全員の顔が見渡せて、和気あいあいとしたアットホームな雰囲気になります♪
家族•親族のみの少人数ウェディングに、ぴったりなレイアウトです^^
▪️「オーバル型」のデメリット
ゲストの人数が多い場合、テーブルの大きさも大きくなってしまい、新郎新婦とゲストの距離が遠くなってしまうため会話がしにくいというデメリットが。
「オーバル型」は少人数のウェディングに適しているレイアウトです^^
レイアウト決めの基本ルール
ここまで、テーブルレイアウトについて種類と特徴をご紹介してきました。
続いては、どのレイアウトでも共通するテーブルレイアウトの基本ルールをご紹介したいと思います^^
▪️新郎新婦のメインテーブルに向かって、左側が新郎のゲスト、右側が新婦のゲストになるように配置する。
▪️ 新郎新婦に最も近い席が「上座(上席)」、最も遠い席が「下座(末席・まっせき)」となる。
肩書き別に表すと、上座から以下の順になります。
•主賓
•会社や職場の上司(目上の方)
•学生時代の恩師
•会社や職場、学生時代の先輩
•友人・同僚
•後輩
•親族
•両親、兄弟
両親や兄弟などの座席は、ゲストをもてなす側になるので、席は下座になります。
また、親族については関係が遠い親戚や年配者ほど上座となるように配席します。
ただし、会費制ウェディングを行う北海道や東北地方などでは、親族や家族が上座に座るのが一般的となっていたり、近年は上座・下座にこだわらないケースも増えてきました。
地域によっても風習が異なるので、迷ったときは式場のプランナーに相談してみるのがオススメです^^
こんなときはどうする?悩み別解決ポイント!
テーブルレイアウトを決めるときに悩みがちないくつかのケースと、その解決ポイントもご紹介したいと思います^^
【1】両家のゲストに人数差があるときは? 【2】同じグループのゲストが同じテーブルに収まらないときは? 【3】ひとりで出席するゲストがいるときは? 【1】両家のゲストに人数差があるときは? どうしても新郎側と新婦側のゲストの人数に差が出てしまう場合には、相手側のスペースにテーブルを配置しても構いません。 また、ひとつのテーブルに両家のゲストが同席しても問題ありません。 メインテーブルに向かってテーブルの左側を新郎ゲスト、右側を新婦ゲストにあてるといいでしょう。 その場合、新郎側の主賓や上司のテーブルに、新婦側の友人が同席するといったことがないように、同席するゲストの位は両家で揃えるようにしましょう^^ できれば同じくらいの年齢の人でまとめたり、趣味や話が合いそうな人を近くに配置するのがオススメです♪ 【2】同じグループのゲストが同じテーブルに収まらないときは? 学生時代の部活のメンバーなど、大人数のグループを招待する場合、全員が同じテーブルに座ってもらうことは難しいケースもあります。 そのような場合、例えば9人のグループなら5人と4人という感じで均等に人数を分けて、近くのテーブルになるように配席するのがオススメです♪ また、「6人用のテーブルに、どうしても7人配置したい…」という場合は、まずはプランナーに確認を。 1席程度なら席を追加できることもありますが、この場合ゲスト同士の距離が近くなり窮屈な思いをしてしまう可能性も。 もし、1テーブルあたりの席数を増やす場合は、事前にゲストにも伝えておくなどの配慮をしておくと安心です^^ 【3】ひとりで出席するゲストがいるときは? 知り合いがいない中、ひとりで結婚式に出席するゲストは不安な気持ちもあるはず。 その場合はゲストが孤立してしまうことがないよう、 ・同じくひとりで出席する人がいる ・話し上手な人がいる ・年齢が近い人でまとまっている ・趣味や好みが似ていて話が合いそうな人がいる 上記のようなテーブルに配席するようにしましょう^^ また、もし幼なじみのように家族と交流のある友人であれば、親族席に座ってもらうのもオススメです♪
最後に
今回は「テーブルレイアウトのルール」についてご紹介しました。
先述したように、披露宴の席次には上座・下座といった基本のルールがあります。
しかし、一番大事なのは「ゲストが心地よく過ごせる空間をつくる」こと。
ゲストに失礼のないように基本的な配席マナーを押さえつつ、状況に応じて柔軟に対応を心がけてみてくださいね^^